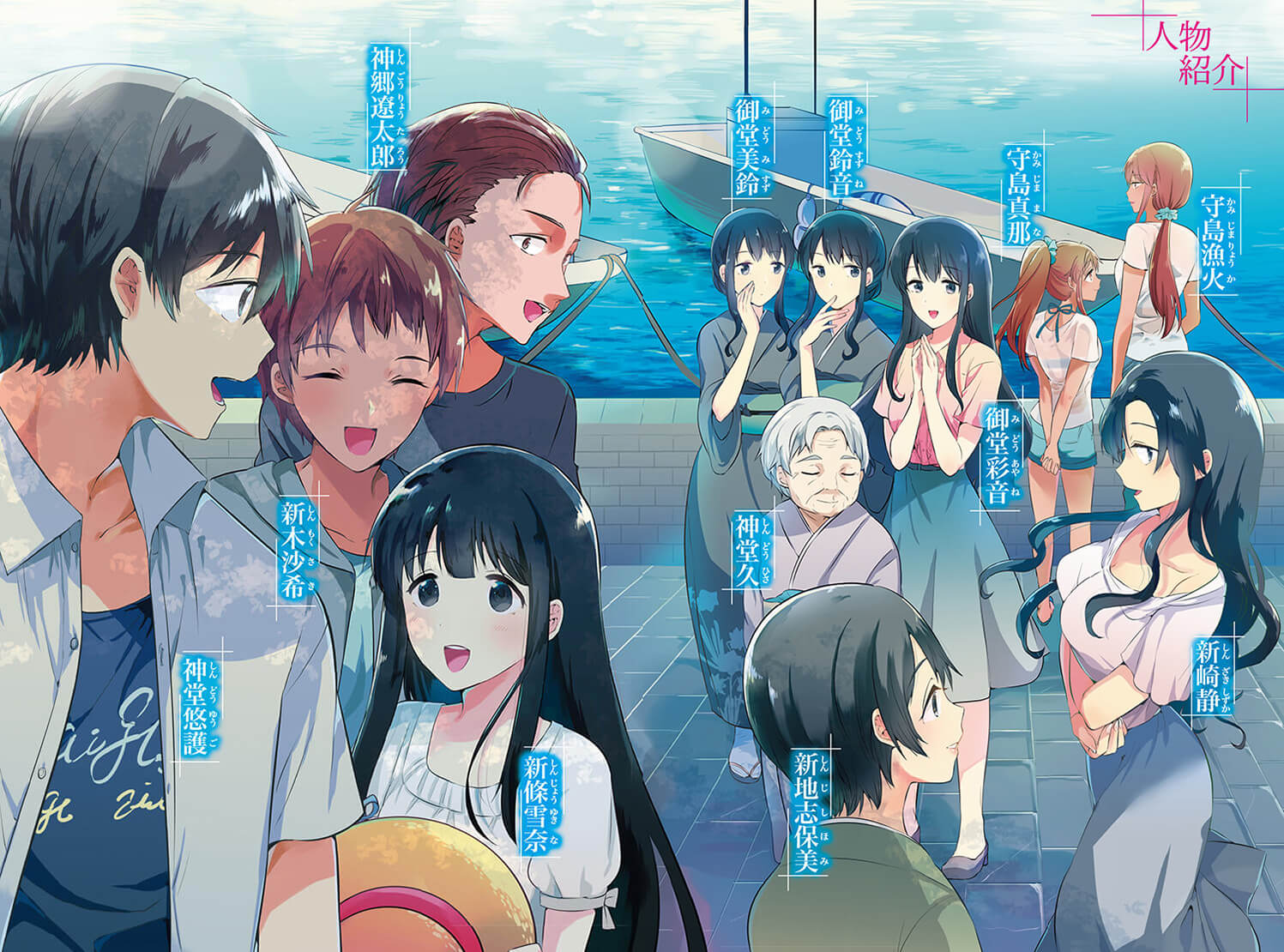「今日もいい天気ですね」
「……そ、そうですね」
ラッキーと言えばラッキーな翌日、俺は彩音さんとともにこの山之島を散策に出かけていた。
天気は晴れ、とはいえ昨日よりはやや涼しくなったのか、暑さはそれほどきつくない。
だがしかし、俺の背中はすでに緊張でべとべとの汗まみれだった。
ほとんど記憶の残っていないこの島を、暇つぶしがてら散策するため一人で出かけようとしたのだが、強引な久さんの薦めもあって、彩音さんに案内してもらうことになってしまったのだ。
あんなことがなければ、こんな美人と二人きりだなんて大変嬉しいおせっかい。しかし昨夜の記憶がちらつく俺にとってはそうじゃない、そうじゃなかった。
少し前を歩く彼女の背中がなんだか透けて見えてしまう。
軽く左右に揺れ動く、彼女のお尻も透けて見えてしまう、ような気がする。
気まずさが半端ない。見なければよかった、ちゃんとノックなり声をかけるなりすればよかった。などという後悔はすでに後の祭りで、昨夜のセミヌードと重なってしまう彼女の後ろ姿に、俺はぎこちなく返事をするのでやっとだったのだ。
サンダルなのに思いのほか彩音さんの歩みは早かった。
さすが、ここに住んでいるだけはあるのだろう。シューズをはいている俺よりも軽快な歩みだった。
昨日よりややタイトな洋服姿の彼女は、時折立ちどまりながら俺を振り返る。
ふわっと風に舞うような長い髪はしっとりとした艶やかな黒色で、シャンプーとかリンスとかその手のCMを見ているかのようだった。
身体のラインが少しだけ分かるような服を着ている彼女の揺れる大きな胸がとても眩しくて、そんな彼女に照れる俺はつい目が泳いでしまう。
彩音さんは思ったより饒舌なのか、指を差しながらそんな俺に道を教えてくれていた。
心なしか彼女は少し浮かれているような気もする。
昨日話した時よりも声のトーンが高いし、なによりとても楽しげだったのだ。
ひょっとしたら彩音さんってば俺のこと……。
いや、ないない勘違い勘違い。俺の一方的な都合のいい思い違いに決まってる。
だってこんな美人さんが、理由もなく俺にそんな気持ちを抱くはずがない。
そう、そんな簡単に好意を持ってくれるはずはないのだ。ましてや昨日会ったばかりなのだから。
「……悠護さん?」
「え? あっ……ッ!」
どうやらぼんやりしていたようで、立ちどまってしまっていた俺の顔を覗き込む、彩音さんのほとんど日に焼けていない顔が目の前にあった。
──ちかっ! 近い近いっ!
彼女の黒い瞳が日の光を受けてキラキラしている。長いまつげまではっきり見えている。それになにかとても甘い感じのいい匂いがする。
この香りってボディソープだろうか? たしかお風呂場に置いてあったのと同じ匂い。
あれ、普通に俺も使っちゃったんだけど、同じの使ったのだろうか?
男に対して無防備なのか、それともひとつとはいえ年下な俺は男に入ってないのか、彩音さんは無警戒にも自然な感じで俺の前にいた。
すぐ手を伸ばせばあの身体に触れられる。
思わず手を上げて彼女の肩に触れかけて、ハッと俺は我に返った。
「あの、大丈夫ですか?」
「は、はい……ええと、ちょっと疲れたかなって……」
「そうですよね、ずっと歩き続けていましたから。この先に見晴らしのいい場所があります、少し休憩しましょうか?」
俺の内心の葛藤に気がつかない彼女は、にっこり微笑むと俺の手を取った。
柔らかい彩音さんの手は、彼女も少し汗をかいていたのだろう、なんだかとてもしっとりしている。
そのまま彼女に手を引かれ──思ったより力が強いのかグイグイと引っ張られて、着いた所は彩音さんの言うとおり、木々の間に八畳ほどのスペースがある見晴らしのいい高台の一角であった。
流れてくる強めの風が気持ちいい。繋いだままだった彼女の手が離れていく、それはなにか残念だった。
その代わりに差し出されたのは水筒である。
「どうぞ」
「あ、すみません」
ニコニコしながら差し出された水筒はコップのついてない直接飲むタイプだった。手の感触に心残りはあれど、それを受け取った俺は、口をつけてゴクゴクと水を飲む。
冷たくてとても美味しい。気のせいだとは思うけど、なぜか仄かに甘い気もする。
「……これって、確か井戸水でしたっけ?」
「ええ、ここは水道がありませんから、飲み水は全部井戸ですよ。水道水より美味しいと思いませんか?」
「はい、冷たくて美味しいですね、水道水とは全然違いますし……売ってるミネラルウォーターより格段に上ですよ、ここの水は」
「あら、うふふ」
俺がそう返事すると、まるで自分が誉められたかのような照れた感じの笑みを浮かべ、彩音さんが笑った。
思ったとおり、笑顔が可愛い。
落ち着いていて大人っぽい雰囲気の彩音さんの照れた微笑みは、年齢よりも幼い感じの可愛らしさを残した、惚れてしまいそうな笑顔だったのだ。
というか実際、昨日一目惚れしちゃったようなものなんだけど。
昨日のこと、そしていまのこと、どうにも落ち着かない気持ちになる俺はもう一口水を飲む。
すると彩音さんはそっと俺から水筒を受け取ると「私も喉が渇きました」などと言いながら、なんのためらいもなく口をつけ、そして再び俺に水筒が手渡される。
唇に水がついたのか指先でそっと拭う仕草の艶やかなこと、俺は飲み口──俺が口をつけ、彩音さんが口をつけたその場所をじっと見る。
──いいんだよね? 間接キスぐらい気にする歳でもないんだし。
俺は彩音さんのぷるっとした艶やかな唇を盗み見ながら、その感触を想像しつつ口をつけるのだった。
三時間ほど歩きまわった俺と彼女は屋敷へと向かっていた。
むろんすべての場所をまわったわけではない。三時間程度でまわり終えるほど狭いわけではないのだ。幾つかある山や一部の海岸線などを含め、島の南東部分を少し教えてもらっただけである。
山では北の方にある神郷神社を遠目に見て、海岸線では海を隔てた向こう側、この山之島より大きいものの人の住んでいない仁之島を見た。
その島はこの海域で一番高い山である守降山を有し、長いこと噴火したことがないのだとも彩音さんから聞かされた。
そして散策の帰り道。少し落ち着いて普通に話せるようになってきた俺は、微妙に距離感が縮まった気がしないでもない彩音さんと、神郷神社のある山の麓を歩いていたのだが、そこで突然声がかけられた。
「あっ! 彩音さん、こんにちわぁ~~」
「こんにちは、彩音さん」
「あら? こんにちは、沙希ちゃんに雪奈ちゃん」
神社に至る石段の手前の三叉路で、反対側から現れたのは女の子二人組である。
髪をバッサリと切った感じの元気そうなショートヘアの女の子、片や艶やかな長い黒髪を頭の片側だけ緩く紐で縛っている大人しそうな女の子。二人とも雰囲気は正反対ながらも可愛い娘だった。
この島、守越智群島の女性って美人率が異常に高くないだろうか?
久さんも若い頃はさぞやって感じだったし、隣の島で見た守島母娘もそうだったけど、年代の差はあれど、出会う人みんな美人さんだったのだ。
三人の美人、美少女が目の前で他愛のない世間話に興じているのを見守っていると、長髪の大人しそうな子は少し顔を伏せながらチラチラと俺を横目で窺っていた。
──なんだろう? あれ? なんとなくこの子、そして彩音さんと話してる元気な娘も、見たことあるようなないような?
「……ん? あれ、雪奈どうしたの?」
「う、うん……」
大人しそうな子を雪奈と呼んだ、ってことは元気そうな子は沙希って名前なのか。ユキナとサキ、サキとユキナ。やっぱ聞き覚えがある、そんな気がした。
俺が記憶を探り考え込んでいると、あっと彩音さんが声を漏らす。
「ご、ごめんなさい、話に夢中になっちゃって……あの、この方は──」
俺をそっちのけにしてしまったことに気がついた彩音さんは、あたふたと慌てながら手のひらをこちらに向け紹介しようとしたのだが、それより前に大人しそうな子が口を開いた。
「あの、もしかしてゆーごちゃん?」
「えっ? あ、はい、そうだけど?」
「ふぁッ!? ゆうご? キミほんとに悠護なの?」
やっぱりというかなんというか、俺はなんとなく会ったことある気がする程度だったのに、二人──特に雪奈さんは俺のことを覚えていたらしい。
しかし一番驚いたのは沙希……さんの方だった。
あれ、なんでだろう? なぜかこの子にさん付けしたくない。
「そうだけ……ですけど」
「うっわ~~、懐かし~~い。ねえねえ覚えてる? あたしのこと?」
「いえ、まったく」
「なっ!!」
ガーンという文字が背後に浮かぶがごとき大袈裟なゼスチャー込みで驚く沙希。
うん、呼び捨ての方がしっくりくる。
「あの……」
「うん?」
くいくいとシャツの裾を引っ張られ、小さな声で言い淀む雪奈さん。
思わず背の低い彼女の頭を撫でそうになる俺はその瞬間、ふと昔のことを思い出した。
それは母が亡くなってすぐの頃、ここに来た俺を慰めようとしたのか頭を撫でる雪奈ちゃんの優しい顔とそのちっちゃな手。
あれ? あの時って確か。
「ゆーごちゃん、大きくなっちゃって……別人かと思っちゃった」
そう、そうだ、確か雪奈ちゃんって俺より背が高かったよな?
どうやらこの十年ちょっとで背丈は抜かしてしまったらしい。
それに子供の頃はなにか着物、そう! 着物を着てるイメージが強かったせいか洋服の彼女を見てもすぐに思い出せなかったんだな、きっと。
なんてことを思い出した俺は、ちょうどほどよい位置に彼女の頭があるもんだから、つい無意識にポンポンと撫でてしまっていた。
とたんに真っ赤になる雪奈ちゃん。
「あ、ごめんつい」
「べ、べつに……大丈夫」
あの頃は彼女のこと、お姉さんみたいに思ってたっけ。けど雪奈ちゃんって、燐と同い年。つまり俺よりふたつ年下なんだよなあ。
ついでに言えば沙希のことも少し思い出していた。
当時は病弱であんまり外出しなかった雪奈ちゃんと違い、野猿のように野山を駆けまわり、イルカのように海や川を泳ぎまわっていたこいつも、燐と同い年。文系気味な大人しい少年だった俺を、妹とともに引きずりまわし、様々なイタズラを受けたことも思い出したのだ。
「……雪奈ちゃん」
「あっ……ゆーごちゃん、私のこと覚えててくれたの?」
「ま、まあ、ちょっと思い出したってゆーか……」
なにか彼女、しゃべり方が舌ったらずというか、年齢より幼い感じがするんだけど、もしかして昔とあまり変わってないのだろうか? いや胸とか身体とかじゃなくて精神的に。
ついそんな彼女と見つめ合っていると、すぐに立ち直ったのか空気を読まない沙希が少し不満そうに話しかけてきた。
「ね、ねえ、あたしのことは?」
「沙希だよな?」
「よ、呼び捨て!?」
「お前年下だろ?」
「そーだけど、雪奈はチャンってつけてるのに、チャンって~~っ!」
「いやなんか……お前そういうの似合わないし」
「むうぅ~~ッ!」
ああ、このやり取り思い出した。昔もこんな感じだったっけ。
こちらもすぐに思い出せなかったのは、昔は腰まで髪を伸ばしてたからだろう。あの頃は野生児そのものだったけど、髪を短くしてるとスポーツ少女って感じがしないでもない。
「……そういえばお二人は悠護さんの小さい頃、一緒に遊んだことがあったんですね?」
「そうで~~すっ!」
「あっ、はいっ……」
「悠護が遊びに来てた時って他にもあたしたちと一緒に遊んだよねえ。守島の真那ちゃんとか、新茄の綾女さんとか、新地の志保美さんとか、 新谷の洋子ちゃんとか……あっ! あとは新崎の静さんとかも──」
「静さんは遊んだっていうより面倒見てもらったんじゃ?」
「あ、そう……だよねえ、そういう意味では五月さんもそうかな~~?」
なにかいっぱい名前が出てきた。
雪奈ちゃんと沙希が思い出話を交えながら語る名前には覚えがない。いや正確に言えば、ぼんやり浮かぶ思い出の中の顔と名前がまったく一致しないというべきか。
ていうかいま出た名前ってみんな女性だよな?
子供の頃の俺は女の子に囲まれて遊んでいたのか、そんなモテモテ君だったのか。記憶に残ってないのが恨めしい、まあ冗談だけど。
小さい頃なんて性別なんかあんまり気にしないだろうし、もしいまだったらハーレムとか言っちゃうんだけど。
ともあれ俺と彩音さんそっちのけで話し続ける二人に口を挟む。キリがなさそうだったからだ。
「……な、なあ」
「ん?」
俺の声にピタリと会話をとめた沙希が振り向く。若干きょとんとした様子のこちらを見る彼女に、俺は無難なことを問いかけた。
「二人はここでなにしてるんだ?」
「あたしたち? いまから神郷神社に行こうと思ってさ」
「……ゆーごちゃんも来る? りょうちゃんもいるから」
「え?」
「そうそう肝心な奴忘れてた! あと遼太郎も一緒だったよね、子供の頃さ」
「そうだったね」
「りょうたろう?」
「ここの神社の息子さんですよ。……そういえば悠護さんと同い年でしたね、遼太郎さんは」
「…………」
「悠護と遼太郎って言えばさ──」
やっと、というか初めて男の名前が出てきた。
りょうたろう──思い出せそうで思い出せないのが本当にもどかしい。
と、今度はそっちの思い出を語り始める沙希と雪奈ちゃん。特に沙希の奴は調子に乗ったのか、ああいう悪さしたとかこういう悪さしたとか、覚えていない俺の幼い頃の罪まで彩音さんの前で語り始めていた。
「……んで悠護と遼太郎、二人で悪さしたらあの優しい五月さんが怒っちゃってさぁ~~」
「──そりゃ張本人のお前が逃げたとばっちりだろ?」
にやにやと悪い笑みを浮かべ楽しげに語る沙希に続いたのは、若い男の声だった。
大声じゃないにも拘らず通りのよいその声に振り向けば、神社の方から下りてきたのだろう、一人の青年が立っていたのである。
「あっ、りょうちゃん」
「うわっ、遼太郎!?」
「こんにちは遼太郎さん」
「よう二人とも……それから彩音さん、こんにちは、お久しぶりです」
俺たちの元へやってきた青年は、男の俺から見ても男前だった。
最近のイケメンって感じとは少し違うけど、サッカーとかサーフィンとか、まあなにかそういう系のスポーツでもしてそうな、日に焼けた彼は俺の方に振り返る。
ちょっと彫りの深い顔、それでいて険の籠ってない優しげな風貌は、俺なんかよりずっと見栄えのいい男だった。
ずいぶん落ちついた感じだしこの辺じゃモテるのだろうか? 美人の多いこの辺でモテモテなのか。
ついじっと見つめてしまっていた俺に、にやっと口元を綻ばせた彼が言う。
「悠護だな? 十年……以上か。久しぶりだな、元気だったか?」
「あ、ああ……」
そのまま軽快に俺の前に歩み寄り、親しげに肩をポンポン叩く彼、遼太郎は友好的だった。
動作のひとつひとつにぎこちなさはまったくなく、そんなごく自然な振る舞いに、同じ男としてちょっと引け目を感じるぐらい安心してしまう雰囲気を持っている。
いうなれば、頼れる兄貴といったところなのだろうか、同い年だけど。
「……悠護ってあんまりあたしたちのこと覚えてないんだってさ」
「ん? ああ、そうか……まあなあ、八歳ぐらいの頃のことはっきり覚えてる奴ってそんないないだろ? それに悠護は本土で暮らしてるんだ。こっちとは違って人もたくさんいるんだろ? 俺らの小学校とか学年で十人ぐらいしかいなかったじゃないか。本土じゃ大勢に囲まれてるんだから、たまに来て遊んだぐらいじゃ記憶の優先度も違うだろ?」
若干不満げにいう沙希に大人な態度で諭す彼は、やっぱり立派になっているということなのだろうか?
女の子二人と違ってなかなか思い出せない彼のことが引っ掛かる。
「悠護」
「あ、なに?」
「今度はいつまでこっちにいるんだ?」
「ええと、一応夏休みいっぱいのつもりだから来月……九月中は最低いる……かな?」
「夏休み? 大学生か……いいな、最低ってことは長くいるかも知れないってことか? あ、燐のこともあるのかな?」
「ん? あ、妹……燐のこと知ってるの?」
突然彼の口から出た妹の名を聞き返した俺に答えたのは、沙希と雪奈ちゃんだった。
「そりゃ知ってるよ~~」
「たまに会ってるよ、ゆーごちゃん」
「……と、いうこと。こないだ彼女から悠護が来るかもって聞いてはいたけど、いつってことまでは知らなかったみたいだからな、正直それ聞いてなかったら誰だったか分からなかったかもしれない」
「そうなのか……」
遊ぶとこがないとか手紙に書いてあったけど、勉強もせずみんなと遊びまわってんじゃないだろうな? 燐の奴。
「でも燐ちゃんから聞いてたのとはちょっとちがうよね? 沙希ちゃん」
「そう?」
「俺もそう思うな」
「へ?」
違うってなんだ? ほんとなに吹き込んだんだ? あいつは。
「う~~ん、モサッとしただらしない兄貴……とは言ってたけど」
「でも違うよね……ゆーごちゃん落ち着いてて大人っぽくて……燐ちゃんが言ってたのとは全然違うよ」
「ガキの頃はひょろっとしてたけど、いまは違うよな……なんかスポーツでも始めたのか?」
燐の奴め。それにしても沙希は置いといて、雪奈ちゃんの俺を持ち上げる感じがこそばゆい。
遼太郎も雰囲気からしてお世辞とかじゃなく本心で言ってるみたいだし。
ひょっとしてここじゃ俺の株、高いのかな?
「いや、特には……ああ、水泳少しやってるけど部活とかサークルじゃなくて、たまにスイミングスクールに顔出すぐらいだけど」
「水泳か、全身運動だよな」
「お、おお……す、水泳……」
「な、なんだよ沙希?」
いきなり呻く沙希は、ぶるぶると震えるとパッと両手を上に挙げた。
「泳げるようになったんだ!! あんた泳げなかったのに!!」
「……中学ぐらいから普通に泳げるようになってたけど」
「そっか、そっかあ……なら今度泳ぎいこう!」
「は?」
「ちっちゃい時ってさ、悠護泳げないってんで砂浜までしか行かなかったじゃない? 海ん中も入れなくてさ、あれ心残りだったんだよね~~。案内したいとことかあったのに」
「そ、そうなのか?」
「そうそう、だから行こう!!」
ああ、そうだそう。こんな感じでみんなをいろんなとこに引っ張ってたのはこいつだった。
海か、悪くはないと少し考えていると、雪奈ちゃんと遼太郎が後押ししてきた。
「ゆーごちゃんが行くなら私も行く」
「いいね、最近ストレス溜まってたからたまには息抜きしたいと思ってたとこだ……遊べば悠護も俺のことを思い出してくれるかもしれないしな、なっ?」
思い出してないことがしっかりバレている。でも嫌そうじゃない、こういうとこ顔に出さないのも大人な男って奴なのか。
結局、その場では遼太郎のことを思い出せなかったが、三日後に海に泳ぎに行くことになった。
女の子たち、まあ遼太郎もいるけど、みんなで一緒に海に行く。そんなの学校の海水浴行事以来の出来事だ。ちょっとわくわくしてしまう、一応海パン持ってきて正解だった。
しかし、その場にいた彩音さんも誘ってみたのだが、家のことがあるからと素気なく断られたのは残念だった。
彩音さんの水着とかぜひ見てみたかったんだけど。
久しぶりの幼馴染みである彼女たちとの再会で、少しテンションが上がっていたのだろう。その夜、俺はなかなか寝付けなかった。
渇きを覚えた喉を潤すため、同じヘマはしちゃまずいとしっかり覚えた道順通りに台所へ向かう。
戸板を閉めてない縁側沿いの廊下を進めば、昨日にも増して月明かりが明るかった。
何事もなく台所にたどり着き、蛇口の栓──ではなくポンプの取っ手を何度か押せばジャバジャバと水が出る。少し流した後でコップに汲み、こくこくとそれをあおった。
「……ッ、ふぃぃ~~」
やっぱ美味しい水だ、適度に冷えてて渇いた喉や胃に染み渡る。
井戸水の方が水道水より美味しいとは聞くけれど、ほんとこんなに違うとは思わなかった。
それにしてもやっぱりこれ、少し甘みがあるような気がするんだが、そんなものなのだろうか?
食器類を使ったら浸けておくだけでいいと彩音さんに言われていたのでそのとおりにし、部屋に戻ろうと暖簾をくぐった時だった。
「……ん?」
廊下に出てすぐ左に曲がった先の暗がりに、ぼんやりと人影が立ってるように見えたのだ。
背丈の感じからして彩音さんかな、と口を開きかけた瞬間、背後から誰かに抱きつかれ口を押さえつけられる。慌てた俺が振りほどこうとしたのだけれど、それは遅かった。
わずかな、ほんのわずかな刺激臭……嫌な臭いじゃない、どこかで、いつか嗅いだことのあるような……そして俺はあっさりと意識を失った──。
ぼやっとする頭、なんだかちょっと身体がフワフワする。
気持ち悪くはなかったけど、妙に重いまぶたを開ければ、同時に聞こえてきたのは彩音さんの声だった。
「ゆ、悠護さん! 大丈夫ですか?」
「あっ……」
凄く心配そうな声、ちょっと悲しそうな響きが心に痛い。
そのせいか急速に覚醒した俺の目の前にいたのは、やっぱり彩音さんだった。そしてその後ろにぼやっとふたつの人影も見えていた。
まだ少し混濁する記憶の中、誰かに襲われたことを思い出し焦って身を起こそうとするのだが、なぜか身体に力が入らない。
「悠護さん、まだ寝ていてください」
「あ、彩音さん、う、後ろ」
「あっ、そ、その……」
あれ? 知ってるのか? ならば大丈夫なのかな? いやでも彼女に危険が、などと考えが巡る中、どうにもすまなそうな表情をする彩音さんが口を開く。
「すみません、私の姉が……」
「え? お姉さん?」
いったいなにを言ってるのだろう? なんのことかと聞き直そうとすると、別の女性の声が聞こえてきた。
「……すみませんでした」
「申し訳ございません……」
ほぼ同時に聞こえた二人分の女性の声は、とてもよく似た響きだった。
やっと視界や頭もしっかりしてきたのか自分の状況を確認する。
ここは俺に宛がわれた客間のひとつ。布団に寝かされた俺を、彩音さんが心配そうに覗き込んでいた。
電灯は灯ってない、電気がないのだから当然だ。それでも窓の障子越しに入ってくる月明かりでぼんやりと部屋の様子は見えている。
彩音さんの背後には人影が、それは間違いなく二人の女性だった。本当の色はともかく、黒っぽい和服を着た女性──どことなく彩音さんに似ている気がする。しかも二人は鏡合わせのようにそっくりだったのだ。
そして彩音さんが言っていた「私の姉」という言葉。
俺が水を飲みにいって背後から襲われた。
前にも人影、つまり二人。……えっと、まさか?
「あの、どういうことで?」
状況と流れはなんとなく把握したのだけれど、なんで? のところが分からない。
彩音さんはちょっと言いづらそうにしているし。
で、俺の質問に答えたのは後ろの二人の方だった。
「悠護様がいらしたと聞いて」
「たまたま台所でお見かけしたのでちょっと驚かそうと」
「…………」
要するにだ、ここまで話を組み立てれば。
彩音さんには二人の姉がいた。
俺がここに来ているのを聞いた。
台所にいるのを見かけ、茶目っ気を出して俺を驚かしたら気を失った。
それで部屋に運ばれて、彩音さんも来て、いまに至る……ということなのだろうか?
分かってしまえば、彩音さんのお姉さんたちということもあって、なんだか怒るに怒れない。
「姉が、姉たちが失礼なことをして本当にすみませんでした」
「あ、いえ、不審者じゃなくてよかったです。彩音さんも襲われたらとか思ったらですね……そ、その……」
「え? あ、ありがとうございます」
ちょっと驚いて、それから頬を赤くして、なんだか嬉しそうで、やっぱりこの女性純粋なんだ。
なにかいい感じに見つめ合ってしまった俺たちに、また声がかけられる。
「……彩音」
「いい雰囲気のところすまないのですが……」
「えっ!! あ、ね、姉さんたち!?」
「私たちの名前だけでも」
「お伝えしてよろしいでしょうか?」
「…………」
まあ、そりゃそうである。
改めて彩音さんと入れ替わるように前に進み出て来たのは、やはり彼女とよく似た顔の、そして瓜ふたつな女性たちだった。
黒い喪服のような着物を着て、手には黒い手袋をはめていたその二人は、本当に見分けがつかないほど、鏡合わせのようにそっくりだったのだ。
彩音さんと比べると、どうにも作り物のような、どこか無機質なものを感じてしまうそのお姉さんたちは、一人ずつ正座したまま頭を下げて名前を告げてきた。
「御堂鈴音です」
「御堂美鈴です」
「えっと、神堂悠護です」
「「存じております」」
「…………」
彩音さんとは別の意味でやりにくい気がする。
「悠護さん、鈴音姉さんは鈴の音と書いて鈴音と読みます。美鈴姉さんは美しい鈴と書いて美鈴と読みます」
「「彩音は彩りの音と書いて彩音と読みます」」
「…………はい」
それは知っている。この二人、別にふざけてるわけじゃないと思いたい。
「鈴音姉さんと美鈴姉さんは見てのとおり双子なんです」
「「彩音は私たちの妹で一人しかいません」」
「はい……」
やはりふざけてるのだろうか?
聞けば鈴音さんと美鈴さんはともに、彩音さんよりふたつ年上の二十四歳で、彼女たちの母親、まだ会ったことのない美影さんという人が神堂家の一切を取り仕切り、二人はその手伝いをしているとのことだった。
そう聞くとやはり神堂家ってこの地方の権力者なのだなあと改めて思ってしまう。
他人事みたいだが俺はそんな旧家、地元の有力者の孫なのだ。まったく実感が湧かないのは、家を出た母の息子であり、親父もこの島の出身とはいえ神堂の名字だけを受け継いだ婿だからだろうか?
しばらくその二人のお姉さんとお話しした後、彼女たちは大人しく去っていった。
彩音さんは俺についていたそうだったのだが、正直見つめられたままじゃ眠れそうにない。なので身体が普通に動かせるようになるまで一時間ほどおしゃべりして、その後は部屋に戻ってもらったのであった。
ちなみに俺が台所に向かってから二時間ほど過ぎていた。ということは一時間近くも俺は気を失っていたことになるのだが、そんなに長いこと彩音さんに付き添ってもらったのか。
「……あれ?」
シーンと静まり返る部屋の中、俺が違和感を覚えたのは、壁に掛けられていた寝間着が目に入ったときである。それはどう見ても俺が着ていたはずのモノだったのだ。
まさかと思いタオルケットをめくれば、なにも身に付けてない見慣れた身体があり、さらに見渡せば文机の上には、俺のトランクスがきちんと畳まれて置いてあったのである。
「……脱がされちゃった? まじで全部、見られちゃった?」
愕然としてしまう俺は自分に対して確認するかのように呟いていた。
もしかして、もしかしなくても彩音さんに見られてしまったのか?
昨日彩音さんの半裸、いや、全裸寸前まで見ちゃってるからこれでおあいこか。
それにそもそも脱がせたのは、彩音さんじゃなくてお姉さんたちのどっちかかもしれないのだ。
でもあの二人だとしても、年上とはいえ若い女性には違いない。
混乱する俺は、巡る思考と時間が経つにつれ無性に恥ずかしくなってくる。
──ああ、もう寝よう、全部忘れよう。
そう思いタオルケットを頭から被るも、やはりなかなか寝付けないのであった。
「──ねえ悠護、大丈夫?」
「あ、ああ……」
「ゆーごちゃん、元気ないけど平気?」
「……大丈夫、大丈夫、問題ないよ……うん」
御堂の三姉妹の誰かに下半身を見られただろう翌日、沙希の奴が雪奈ちゃんを連れて屋敷にやって来たのだ。アポなしで、しかも早朝に。
昨夜の一件が忘れられない俺は、雪奈ちゃんはともかく沙希にまで心配されるほどだった。当然なにがあったのかは話していない。話せるわけがない。
とはいえいつまでも気にしていても仕方ないと思い直し、気分転換も兼ねて二人に山之島の北側を案内してもらっていたのだ。
で、なぜか俺は二人と手を繋いでいた。
俺を元気づけようとしたのか、右手を雪奈ちゃん、左手を沙希が握り、二人は楽しげに案内してくれていたのである。
「──あの小さい方の山が北の山、神郷神社があるんだ」
「地元の人は沙希ちゃんみたいに北の山って呼んでるけど、正確には向山って名前なの」
?「へ~~」
「こっちからだと見えにくいけどさ、南側には南の山があるんだよっ」
「まんまだね、ってそれは昨日通ったとこ?」
「うん、そう……そっちは拝高山って言うんだけど、やっぱりみんな南の山って呼んじゃってるの」
「なるほど」
「他にも山はあるけど、あのふたつが目立つんだよね」
「うん、北と南でそれぞれ一番高い山だからなの」
「ほーー」
「あっ! そこの横道入って、さあ行こーー」
「えっ、おおぅ!」
「あっ! 沙希ちゃん、急に引っ張らないでよ」
唐突に沙希が横道に逸れ、俺の手を引っ張りどんどん進んで行く。当然俺の反対側の手を握る雪奈ちゃんも一緒に引っ張られていた。
まあなんというかこうして沙希が俺の手を取って引っ張りまわすものだから、雪奈ちゃんも対抗しようとしたのか反対側の手を握っていたのだ。
しかしいいのだろうか? もう子供じゃないのに手を繋ぐとか、しかも両手に花状態。冷静を装ってはいたけれど、照れくさくて仕方ない
二人は今日も、昨日会ったときと同じような服装で、雪奈ちゃんは麦わら帽子に白系のワンピース、それが大人しそうな彼女にとてもよく似合ってた。
一方の沙希はといえば、半袖パーカーに下はTシャツ、それと太ももがよく見えるデニムの短パンをはいていた。こっちも元気な彼女によく似合ってる。
そんな沙希が俺たちを引っ張り込んだ先は、森から抜けた先にある丘のような所だった。
たぶんここは島の北東部。大変見晴らしのいい高台で、俺の手を離しくるりと半回転する彼女はジャーンと言わんばかりに解説を始めるのだった。
彼女の話は抽象的だったが、逐一フォローを入れてくれた雪奈ちゃんのおかげで理解できた。
ここから見下ろした先にあるのは海岸線、手前には数軒家が建っていて、周りを畑が囲んでいる。
その畑はあまり広くはない。聞けば主に芋類とか根菜類とかを育てていて、売り物じゃなく村で全部消費しているとのことである。ちなみに海に一番近くにあるのが沙希の家。神堂の屋敷を見ちゃうと小さく感じるけど、よく見れば結構でかい。
今度遊びに来なよと言う沙希。そして当然のごとく、私の家にもと言う雪奈ちゃん。彼女の家は、神堂のお屋敷と同じエリア、島の南東寄りにあるとのことだった。
女の子の家、女の子の部屋。それは大変興味があるのだが、二人の家族に会うのはちょっと気が引ける。
なので無難にまたいつかと答えた俺はチキンなのだろうか? こういうとき男前なら、例えば遼太郎なんかはなんて答えるのだろう?
それはともかくも、二人が島の案内や解説をしてくれるのはありがたい。そもそも村のことについて俺が知ってることが少なすぎた。せいぜい守越智群島には、ここ山之島の守越智村と隣の志之島の守前村のふたつしか存在しないという程度だったのだ。
沙希と雪奈ちゃんが解説を終えるタイミングを見計らって、俺は村のことを聞いてみた。
「なあ、守越智村ってどのくらいの人が住んでるんだ?」
「う~~んと、何人ぐらいだったかな? 百人ぐらい?」
「五十三人、住み込みで働きに来てる佐藤さんを入れると五十四人、ゆーごちゃんと燐ちゃん入れて五十六人になったんだよ」
思ったより少ない。
まあ、こうして歩いていてもほとんど村の人に会わないし、そんなものなのだろう。
というか佐藤さんて誰?
「そんなに少なかった? あたしもっと多いかと」
「沙希ちゃん、そんなの数えればすぐ分かることでしょ?」
「だよなあ」
「うっ、ま、まあいいじゃない!」
自分の住んでるとこの、しかも五十人ぐらいしかいない村人の人数も数えられないのか。
「向こうに見えるのって志之島だよな?」
「うんそう、面積はこっちの方が倍ぐらい広いんだけど、向こうは千人ぐらい住んでいて──」
「……守前村の人口は四百八十九人だよ。沙希ちゃんこういうこと興味ないからって適当すぎるよ」
「ぐっ……し、知らなくても別に困んないし」
「沙希らしいって言えば実に沙希らしいけどな」
「あたしたちのこと、ほとんど忘れてた悠護には言われたくなーーい!!」
全身を使って沙希はゼスチャーじみた否定をする。
そんな彼女の様子に俺の手を握ったままの雪奈ちゃんがくすくすと笑う。
島の穏やかな雰囲気にマッチした、実に心地よいやり取りである。
それにしても雪奈ちゃんってこんなに懐いてくれて、もしや俺のこと……なんて思ってしまう。きっと子供の頃の延長線上って感じで、久々に会った幼馴染みの俺が懐かしいんだろうけど。
沙希は、たぶんこれが平常運転なんだろうな。
真那さんほどじゃないけど、沙希はしっかり日焼けしてる。対して雪奈ちゃんは日焼けをしていない。
色々肌のお手入れとか日焼け止めとか気を遣っているんだろう。なんとはなしにじろじろと見てしまった俺と目が合い、彼女の頬が少し赤くなる。
やっば変な意味じゃなく緊張してるんだな。というかお年頃の娘を無遠慮に見つめるとか失礼すぎた。
「あ! 沙希ちゃんてばまた!」
「んむっ、むむぅ?」
「あ? なに食ってるんだ?」
「ん……野イチゴ、甘酸っぱくて美味しい」
「食べるのはいいけど、ちゃんと洗ってからにしようよ」
ほんの少し目を離した隙に、口をもごもごさせていた沙希は雪奈ちゃんに怒られて、バツが悪そうにてへへと愛想笑いをしていた。でもまあこういうのって田舎に来たなあって感じがするし、悪くはない。
それに空気を改めてくれた意地汚い彼女に感謝もせねばなるまい。
「……そんなに美味いのか?」
「まあね」
「俺もひとつ」
「ほい」
「ゆ、ゆーごちゃんまで」
「まあまあ、何事も経験というか、俺もちょっと味見をば」
「も~~」
ちょっと唇を突き出し気味な雪奈ちゃんは可愛かった。
そんな彼女を横目で見つつ、沙希から一粒貰ってポイッと口の中に放り込んで咀嚼したのだが──。
「……す、酸っぱい」
「甘いもの食べ慣れてるからそー感じるの」
「そ、そういうものか?」
「雪奈も甘いって思うよね、これ」
「うん」
知らないうちに味覚が鈍くなってたのか? 酸っぱさだけで全然甘く感じなかった。
その後、北の山をぐるっとまわって戻ってきた俺たちは、再び島の北東部にたどり着く。
「つ、疲れた……」
「三時間ぐらいしか歩いてないけど?」
「三時間も、だろ?」
「ゆーごちゃん、身体なまった?」
「……すみません」
道はあっても整地されてないから歩きにくいんです。
沙希はともかく雪奈ちゃんにまで言われてしまった。凹む俺に沙希が水筒をそっと差し出す。
「ん? なに?」
「水だよ、水分とらないと」
「あっ、すまない」
言われてみれば確かに喉がカラカラだった。水筒を受け取るとゴクゴクと水を飲む。
あーー冷たくてうまい、生き返る。
そんな俺を見ていた雪奈ちゃんもそっと水筒を差し出してくる。
「私のも……飲んで、ゆーごちゃん」
「え? あ、うん」
すでに飲んだんだけど、なんだろう? 普通に差し出してきてるのに断れる雰囲気じゃなかった。
沙希に対抗してるのか? なんだか黒いオーラが雪奈ちゃんの背後に……なんてな。
せっかくなので雪奈ちゃんからも受け取ると、今度はゆっくり、味わうように水を飲む。
やっぱ美味しい。これって井戸の水だよな、少し甘い気がするのが同じだった。
「ふぅ~~、二人ともありがとう」
「うん」
「気にしないで」
俺から水筒を受けとると、二人とも飲み口を少し見つめた後にごくごくコクコクと飲んでしまう。
あ、間接……まあ、彼女たちが気にしないなら別にいいか。
それにしても雪奈ちゃん、顔が赤くなって口元もニヤけてるような気がしたのは、俺の気のせいだろうか?
「みんな水筒持ち歩いてるの?」
「そうだよ」
「じょーしきだよ、じょーしき」
沙希に常識なんて言われてしまった。
でも確かに、彩音さんも持ってたし、ここじゃみんな持ち歩くのが普通なのだろう。ほとんど山道っぽいし、コンビニはおろか自販機だってないのだから、手ぶらな俺の方が甘く見すぎてるのに違いない。
「出歩くときはみんな水筒持つのがここの流儀なのだ」
「なのだ、ってなんだよ」
「そうなのだ」
「沙希ちゃんて、たまに変なこと言うよね」
「沙希らしいといえば実に沙希らしいけどな」
「また言った!! ていうか変ってなに!!」
他愛のないことを二人としゃべってると、昨夜のことがだんだん気にならなくなってくる。
能天気な沙希と、優しい雪奈ちゃんのおかげだ。
そんなこんなで沙希の家と神堂の屋敷の分かれ道まで戻ってくると、雪奈ちゃんがすまなそうに話しかけてきた。
「あの……午後から沙希ちゃんの家の手伝いしなきゃいけないの」
「手伝い?」
「草むしりめんどい~~」
「もうお昼だし、今日はここでゆーごちゃんとお別れしなきゃ」
「家の手伝いならしょうがないよ、そんなすまなそうにしないでも」
「で、でも」
「また明日……と言いたいとこだけど、あたしたち用事があるんだよねえ~~」
「家の手伝いか?」
「そんなとこ、まあ明後日はいよいよ海だし今日は我慢しようか雪奈?」
「うん……あの、ごめんねゆーごちゃん」
「いいって、俺も海は楽しみにしてるからさ……じゃあ、明後日な」
「うん」
「じゃあね、悠護」
「おう」
ということで、帰っていく二人をしばらく見送った後、俺は屋敷へ向かって歩き出したのだった。
しばらく小川沿いを歩いていると、ちょっとした岩場っぽい所に人がいるのを発見した。
ちょうど座るのによさげな岩に腰掛けて、小川の流れでも見ているのだろうか? なにかこう雰囲気のある女性が一人ぽつんと佇んでいたのだ。
しかもまた美人さんだ、彩音さんよりは年上だろうか?
緩くウェーブの入った艶のある長い髪をそのまま垂らし、少し解れた前髪が頬にひと房掛かっているのがなんとも言えない色気を感じさせる人だった。
「……こんにちは」
「こんにちは……あっ!」
後ろの道を通り過ぎがてら挨拶した俺に返事をしてくれたその女性は、なぜか慌てた感じで立ち上がると駆け寄ってくる。すると石にでも躓いたのか、あと少しというところで俺の方に倒れてきたのだ。慌てて受けとめた俺の胸にしっかり収まった彼女から、ほんのり甘い香りが匂ってくる。
「あ、あの大丈夫ですか?」
「あっ、ごめんなさい」

押し付けられた胸の感触は、彼女の少々だぶついた感じの服の上からでもはっきりと分かるほど。つい先日の漁火さんより柔らかくて、かなり立派な胸だと確信できる。
背中を抱きしめるような体勢で支える俺にしがみつく彼女は、細身ながらとても柔らかく、俺より背が低いのか微妙にうわめづかいなところなんかも、ゾクッとするほど色っぽい。
「……もしかして、悠護くん?」
「え? あ、はい、そうですけど?」
ちょっと眠たげな感じの目を大きく見開いて見上げてくる彼女は、やはりかなりの美人さんだった。
近い距離でそんな美人から直視され、思わず顔が赤くなってしまう。目のやり場に困る俺に、彼女は嬉しそうに話しかけてきた。
「島に来てるって聞いてたけど、ほんと大きくなったわね~~」
「ど、どうも、ええと──」
「え?」
「私の名前、新崎静っていうのよ」
「あっ!」
その名前、つい最近聞いたことがある。雪奈ちゃんたちが小さい頃に面倒見てくれてたとか言ってた人だ。
シンプルな淡いグレーのスカートに、ややダブつきのある薄くピンクがかった長袖のブラウスを着ているこの女性──静さんは俺の胸に当てていた手をなぜか動かして、なんというか妙に艶めかしい感じで撫でまわしていたのだ。
女の人に胸を撫でられるなんて初めてのことで、どうしたらいいものか迷う俺に彼女はにっこりと微笑むと、ようやく少し離れてくれた。
「覚えていてくれたのかしら?」
「す、すみません……名前は聞いていたんですけど、あんまり昔のこと覚えてなくて……思い出せませんでした」
「あらら、でも正直に言ってくれてお姉さん嬉しいわ~~」
両手を胸の前でポンと合わせる彼女は少しも気に障った様子はなく、逆になにか楽しそうだった。
おっとりした雰囲気に、間延びしたしゃべり方、仕草の端々になんとも言えない色気を感じてしまう。
指の動きや視線の動かし方、軽く小首を傾げるところとか、媚びてるとまでは言わないけどそういう細かい部分にドキッとしてしまうものを持つ、なんとも色っぽいお姉さんだったのである。
と、離れたと思ったらすぐに彼女は抱きついてきた。
「え? ちょっ!」
「背丈も伸びたわね~~、昔は私の胸にも届かなかったのにね」
胸という言葉をわざとらしくも強調する静さんは、それをわざと押しつけるように抱きついていた。
「あの、む、胸が当たってるんですけど?」
「うふふ、当ててるの~~」
「ええ!?」
「最後に悠護くんに会ったとき、私十六歳だったんだけど……あの頃より大きくなったのよ」
「そ、そうですか……」
他にどう言えと? 大きくなりましたねとか、立派な胸ですよ、なんて初対面に等しい彼女に言えるはずがない。
「ねえ、どうかな?」
「ど、どうっていわれても」
「ほらぁ、分かる? 私ブラしてないのよ?」
「いッ!」
その言葉に、ぐいぐいと押し付けられていた彼女の胸を思わずじっと見てしまう。
むにゅ、むにゅっと何度も強く押しつけてくる合間の少し離れた瞬間、確かに胸の先端辺りがツンと尖ってるのが見て取れたのだ。
冗談でも嘘でもない、まじでこの人ノーブラである。
「ちょ、ちょっと待って、な、なんでこんなこと? からかってるんですか!?」
「あら、ごめんなさいね~~久しぶりに悠護くんに会ったから嬉しくて。つい、はしゃいじゃったわ~~」
一応恥じらいはあるのか、ちょっと顔を赤らめた彼女はようやく本当に俺から離れてくれた。
代わりに両手を握られてしまったのだけれど。
「ねえ、悠護くん」
「は、はい」
「少しだけ私とお話しない?」
「お話、ですか?」
「うん、ダメかなぁ?」
「……いえ、そんなことないですけど……」
小首を傾げて聞いてくる静さん。さっきの話が嘘じゃなかったら、この人少なくとも二十八歳なのか。とてもそうには見えない。いや、見た目はそうかもだけど、なにか性格的に沙希とは別の意味での子供っぽさを持ち合わせているような感じの人だった。
俺が言い淀んでいる間にも静さんに手を引かれ、さっきまで彼女のいた岩場へと連れて行かれる。
──ま、いっか、お話だけなら……うん。
こうして俺は、突然出会った静さんとお話することになってしまったのである。
「──改めてお久しぶりです、悠護くん。新崎家の静、先月二十八歳になりました」
「あ、どうも、神堂悠護です……二十一になります」
なぜだろう? なぜかお見合いみたいになってしまった、したことなんかないけれど。
岩に俺が腰掛ければ、その横に静さんがぺったりくっ付くように座ってくる。
鼻歌でも歌いそうなぐらい楽しげな彼女は、俺をほんの少し見上げたまま握った片手を離してくれない。
女性らしく小さくて柔らかい手、触り心地がいいというか、凄くすべすべした手のひらだった。
彼女はいったいなにがそんなに楽しいのか、始終にこにこと微笑んでいたのである。
「悠護くんの小さい頃、こうして手を繋いでお散歩とかしたのよ」
「そうですか」
「私より背が大きくなっちゃったみたいだし……いま身長ってどのくらいなの?」
「えーと、百六十九センチかな……」
チビとまでは言わないかもだけど、男としては小柄なままなのだ。
それにしても隣でサンダルをはいた脚を少しぶらぶらさせている静さんのことは、やはり遼太郎と同じく思い出せない。膝下から見える、すらっとした生足が綺麗なのは分かるんだけど。
「気にしなくていいのよ? ちっちゃかったんだもの、覚えていなくても仕方ないわよ~~」
「……すみません」
顔に出てたんだろうか? 俺の心を読んだかのように静さんがフォローを入れてくる。
気まずい、非常に気まずい。
彼女の方が七つも年上ってこともあるんだろうけど、向こうは俺のことを小さい頃と同じように扱っている気がする。成人を迎えた俺に対してそういう態度で来られるのは、嫌じゃないのが余計に恥ずかしい。
俺が黙り込んでしまうと、静さんはちょっと頭を下げ気味に覗き込んでくる。
うおっ! そういう恰好になると弛んだ首の辺りの隙間から、谷間というか丸みの上の部分がふたつとも見えてしまってた。やっぱり大きさも漁火さんより上かもしれない。
ついそんな魅惑の膨らみの、ごく一部を目にしてしまい、耐えきれずに視線をずらせば、覗き込んできた彼女と目が合ってしまう。
「……あっ」
「うふふ」
笑われてしまった。いや照れる俺を微笑ましいという感じで笑いかけてくれたのか。
ああもう、気まずいというかやりにくいというか、なんだか自分自身がじれったい。
そのまま正面を向いた俺に対し、隣で微笑む静さんは俺の方を向いたままだった。
握っていた手とは別の手が、すっと俺の方に寄せられて軽く太ももにも触れてくる。
「胸もだけど足の方も筋肉ついて……本当に逞しくなったのね」
「あ、あの……」
「なにかスポーツでもして鍛えてるの?」
「ええと……水泳を少々」
「そうなんだぁ~~、あっ! ということは泳げるようになったのね?」
「ええ、まあ」
ちょっと前に沙希たちと話したことの繰り返し。
静さんはそのまましばらく俺の太ももを撫でていると、ふっと顔を起こして俺を見る。
少し潤んだような瞳はやはり色っぽい。
薄く塗られた口紅でしっとりとしている唇は、ぷるんとしたとても柔らかそうな代物で、思わず触れてみたくなる……そんな魅力的な唇だった。
「あっ」
思わず小さく声を漏らしてしまう。
横目で顔を盗み見ていた俺に、彼女がまたもや抱きついてきたのだ。
静さんの柔らかくも弾力のある胸がこれでもかと押しつけられていた。俺のTシャツと彼女のブラウスと二枚の布地が間にあるにも拘らず、その感触は俺の胸や股間を昂らせる。
匂いの方も堪らない。ほんのりと漂ってくる彼女の香りはきっと香水かなにかなのだろう。強すぎず弱すぎず、絶妙な加減の甘い蜂蜜のような、とてもいい匂いで頭がクラクラしてきそうだった。
ああヤバい、本格的に股間がヤバい……このままじゃ本当に勃起してしまう。
焦る俺は、しかし彼女の魅力的な身体の感触を、とてもじゃないが振り払うことなどできなかった。
ムクムクと大きくなっていく俺のモノ、それを抑えることなどとてもじゃないができやしない。
もう彼女に気づかれる──そう覚悟した瞬間、静さんはスッと俺から離れていった。
「うふ、悠護くん逞しい~~」
「う……」
にっこり笑う彼女。身体のことか股間のことか、どっちのことを言っているのだろうと考える……いや、身体の方、筋肉付いて少しは男っぽくなった身体のことを言っているのだと自分に言い聞かす。
顔が熱い、きっと真っ赤になってる顔を覗き込むような彼女の視線に、照れる俺はなにも言い返すことができなかった。
唇に人差し指を押し当てて、少し残念そうな表情になった彼女は言う。
「ん~~、もっとゆっくり悠護くんとお話ししたかったんだけど、そろそろ帰らなきゃダメなのよね~~」
「あ、そ、そうですか……」
「うん、そうなのよ……悠護くん、まだこの島にいるんでしょう?」
「ええその、九月いっぱいは……たぶん」
「じゃあ、また会えるわね。あ~~あ、名残惜しいけど行かなきゃ、じゃあね悠護くん、またねえ~~」
「はい……んッ!」
彼女は人差し指を俺の唇に軽く押し当てて、そのまま手を振りながら去っていく。
道の方へと登る彼女のスカートから覗く、真っ白でキュッと締まったふくらはぎについ目が行ってしまう。
ふりふりと揺れるお尻は彩音さんより大きかった。
少し陶然とした感じで見送る俺は、彼女の姿が見えなくなって初めて唇から唇へと押し当てられた静さんの人差し指のことを思いだし、思わず口を手で覆い隠してしまうのであった──。